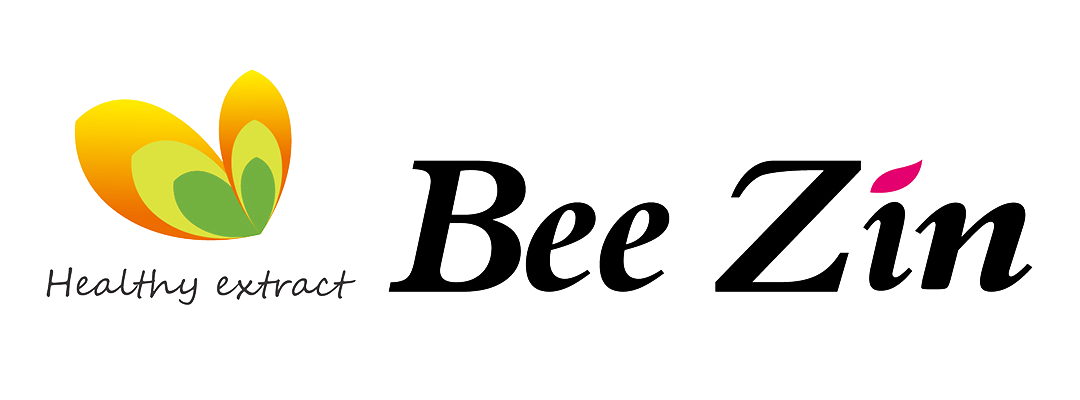"集中する一日"のベースをつくる
受験前のベースを整える3点セット
オメガ3(n-3系)脂肪酸は食べ物からしか摂取できない必須脂肪酸です。体の健康に対して不可欠な栄養素です。
摂取されたオメガ3系多価不飽和脂肪酸は、細胞膜の主要構成成分であるリン脂質に組み込まれ、炎症や活性酸素種の作用を抑制し、血中中性脂肪値の低下、不整脈の発生防止、血管内皮細胞の機能改善、血栓生成防止作用等いろいろな生理作用を介して生活習慣病の予防効果があります。欠乏すると皮膚炎などを発症する恐れがあります。
1. EPA(エイコサペンタエン酸)、DHA(ドコサヘキサエン酸)
魚類、特にいわし、まぐろなどの青魚に多く含まれる脂肪酸の一種。 血液をサラサラにしてくれる働きがあり、DHAとEPAの相乗効果で脳内の血管を健康に保つ効果があります。
●DHA:体内ではEPAからつくられ、脳や神経組織の機能を高める働きがあり、神経細胞を活性化させ記憶力や学習能力を向上させます。脳や神経、目の働きに関与し、記憶力や視覚の維持に大切です。
●EPA:体内で合成することができない成分です。医薬品としても利用されており、血栓をつくらせない成分が多く含まれているのが特徴です。血液をサラサラにし、中性脂肪を下げ、抗炎症作用も期待できます。
2. α-リノレン酸
アマニ(亜麻仁)、チアシード、くるみなどの種実類に多く含まれ、血流改善や動脈硬化の予防に効果的な成分です。体内ではDHAやEPAに変換されますが、10%程度と言われています。アマニは特にその含有率が高いことで知られており、約24%のα-リノレン酸を有しています。
主な効果
心血管系の健康維持
血液をサラサラにし、高血圧・動脈硬化・心筋梗塞などのリスクを下げる効果が期待できます。また、血中コレステロール及び中性脂肪低下作用があり、脂質異常症改善に有効です。
脳や神経のサポート
学習能力や集中力、認知症予防に関与し、胎児・小児の脳機能発達や高齢期の認知機能の維持向上効果が期待できます。
抗炎症作用
リウマチやアレルギー性疾患、皮膚炎の炎症を抑える働きがあるとされる。
視力の維持
DHAが網膜の構成成分であるため、目の健康を守る。
オメガ3(n-3系)を多く含む食品
• 動物性:サンマ、イワシ、サバ、マグロ、サケなど青魚。
• 植物性:亜麻仁油、エゴマ油、チアシード、クルミ。
摂取の目安
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によれば、DHAおよびEPAを含むオメガ3系脂肪酸の一日の食事摂取基準は、12~49歳の男性で2.2g、女性で1.7g、50~64歳の男性で2.3g、女性で1.9g、65~74歳、75歳以上の男性で2.3g、女性で2.0g、とされています。
「1食分の目安量」を以下のように仮定して計算してみます。
・魚(鰯・鯖・鮭) → 1切れ 約80g
・くるみ → 約25g(ひとつかみ)
・えごま油 → 小さじ1(約4.6g)
| 食品 | 摂取量(目安) | n-3系多価不飽和脂肪酸量 |
|---|---|---|
| 鰯 | 80g | 1.68g |
| 鯖 | 80g | 1.70g |
| 鮭 | 80g | 0.74g |
| くるみ | 25g | 2.24g |
| えごま油 | 4.6g(小さじ1) | 2.68g |
| 出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023 | ||
・魚1切れで 約1.5〜1.7g のn-3を摂取できます。
・くるみ25g(おやつ1回分程度)で魚と同じかそれ以上の量が摂れます。
・えごま油は 小さじ1杯 で魚1切れ分以上のn-3を補えます。
注意点
• 加熱に弱いため、油はドレッシングや仕上げに使うのがおすすめ。
• サプリを利用する場合は、過剰摂取(特に3g以上/日)は出血リスクに注意。
• 非常に酸化しやすいので注意が必要です。
⇒「空気中の酸素」「温度」「光」等が原因となり酸化は進行します。
酸化した油脂が体内に取り込まれ蓄積されると、細胞にダメージを与え、動脈硬化、糖尿病、認知症等の様々な疾病の原因になると考えられています。また、酸化した油脂を一度に過剰摂取すると、嘔吐、下痢、腹痛等の症状が生じることもあります。
オメガ6脂肪酸
n-6系脂肪酸には、リノール酸、γ-リノレン酸、アラキドン酸などがあり、γ-リノレン酸、アラキドン酸はリノール酸の代謝物です。n-6系脂肪酸もn-3系脂肪酸同様、体内で合成することができないため、食事から摂取する必要がある必須脂肪酸です。日本人が食品から摂取するn-6系脂肪酸の98%はリノール酸とされており、大豆油やコーン油などの植物油が主な摂取源です。摂りすぎはHDLを低下させ、動脈硬化、心疾患、癌、アレルギーなどのリスクを生じる可能性がある為注意が必要です。
オメガ3とオメガ6の違い
どちらも 必須脂肪酸ですが、働きに大きな違いがあります。
• オメガ6の働き
o 細胞膜の構成に必要
o 成長や皮膚の健康をサポート
※過剰摂取で炎症を促進(アレルギー・動脈硬化のリスク増)
バランスが大事!
オメガ3脂肪酸とのバランスが重要であり、過剰摂取はアレルギー症状の悪化や動脈硬化のリスクを高める可能性があるため、現代の食生活では意識的にオメガ6脂肪酸の摂取量を抑えることが推奨されます。
理想的な摂取バランスは オメガ6:オメガ3 = 2〜4:1 とされています。
必須脂肪酸は肌の水分保持力の80%を担う細胞間脂質の材料でもあるので、不足すると肌の水分保持力が低下します。オメガ6とオメガ3の割合が崩れ、オメガ6の割合が多くなると、乾燥肌になりやすくなります。(実際は9:1以上になりやすく、炎症や生活習慣病の原因に…)
オメガ6脂肪酸は体に必要ですが、摂りすぎ注意の脂肪酸です。
バランス改善の工夫
・揚げ物や加工食品を減らす(オメガ6の過剰を防ぐ)
・青魚を週2〜3回食べる(EPA・DHAを補う)
・亜麻仁油・エゴマ油をサラダや味噌汁にプラスする
・くるみやチアシードなど植物由来のオメガ3を摂り入れる
オメガ3は炎症を抑え、「血管・脳・目・炎症」すべてを守る必須脂肪酸 です。
現代の日本人は、オメガ6を揚げ物・加工食品などで摂りすぎる傾向があります。魚と植物油をうまく組み合わせて、オメガ3を意識的に摂り入れることが健康維持のカギ となります。
参考
- 「日本人の食事摂取基準(2025年版)」 (https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316463.pdf)
- 日本脂質栄養学会 (https://jsln.umin.jp/committee/omega51.html)
- 産業技術総合研究所 (https://dm-net.co.jp/calendar/2016/026158.php?_ga=2.125152770.92898329.1698029830-57174493.1698029830)
この記事は管理栄養士の方に執筆していただきました
井上 希恵