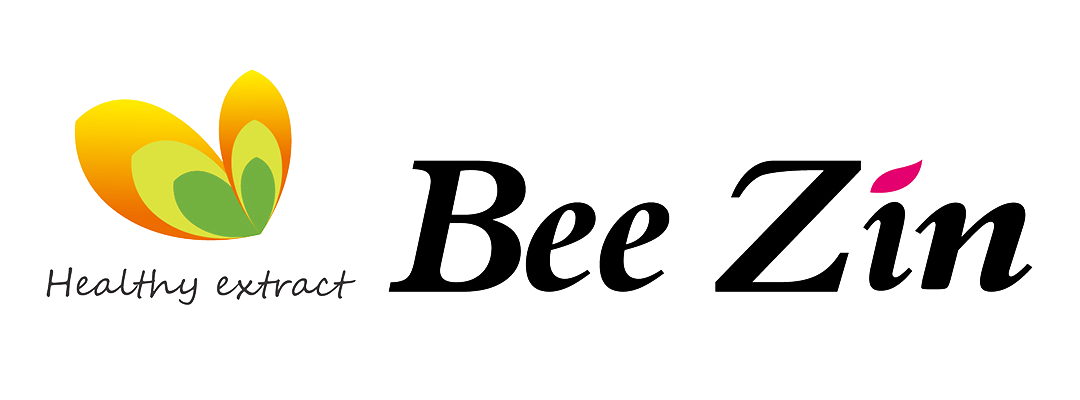"集中する一日"のベースをつくる
受験前のベースを整える3点セット
EPA(エイコサペンタエン酸) は、DHAと同じく オメガ3系脂肪酸 の一種で、青魚(サンマ、イワシ、サバ、アジなど)に多く含まれています。
体内ではほとんど合成できない「必須脂肪酸」で、食事やサプリからの摂取が重要です。
EPAは非常に柔軟性の高い脂肪酸です。日常的にEPAを多く摂取している人の細胞膜にはEPAが豊富に取り込まれ、結果として細胞膜自体も柔らかくしなやかになります。さらに、この細胞膜中のEPAは、炎症を抑制する作用をもつさまざまな物質へと変化し、私たちの体を炎症から守る役割を果たしています。
主な働き
1. 血液サラサラ効果
血小板の凝集を抑えて血液を流れやすくし、血栓(血の塊)を予防。心筋梗塞や脳梗塞のリスクを下げると考えられています。
2. 中性脂肪を下げる
血中の中性脂肪を低下させ、生活習慣病の予防に役立ちます。
3. 抗炎症作用
炎症を抑える働きがあり、関節リウマチやアトピー性皮膚炎、喘息などの症状改善の研究も進んでいます。
4. 月経痛に関与
下腹部の痛みや強い腰痛、頭痛、吐き気、不眠などを伴う月経困難症には、「プロスタグランジン」という物質が関わっています。EPAは、これらの症状を和らげる働きを持つプロスタグランジンE3へと変換され、痛みを抑えるサポートをしてくれます。
EPAを多く含む食品
| 食品 | n-3系多価不飽和脂肪酸量 (mg/100g) |
|---|---|
| サンマ | 1500 mg |
| イワシ | 2780 mg |
| サバ | 1800 mg |
| ニジマス | 600 mg |
| 出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 | |
※EPAは脂の多い魚に豊富です。皮のすぐ下と血合いの部分に多く存在する脂質で、DHAと同じく刺身や煮魚など、油を逃さない調理法が理想的です。
DHAとの違い
• EPA: 血液・血管・心臓に良い影響
• DHA:脳や神経、目の働きをサポート
両方とも一緒に摂取することで、生活習慣病予防や脳機能維持に効果的です。
摂取のポイント
• 厚生労働省の推奨量は EPA+DHAで1日1,400〜1,600mg。
• EPAは酸化されやすい栄養素です。ビタミンEは脂溶性の強力な抗酸化物質なので、ビタミンEと一緒に摂ることで酸化防止できます。ビタミンEはナッツ類やアボカド、カボチャ等に多く含まれます。
• サプリメントを利用する際は、医師や薬剤師と相談しながら摂ると安心です。
• ワルファリンなどの血液をサラサラにする薬を服用中の方は注意が必要です。
EPAは血液・血管の健康を守る栄養素 で、DHAと組み合わせて摂るとより効果的です。
EPAが特に効果的とされる人
EPAは「血液サラサラ」「抗炎症作用」が大きな特徴なので、以下のような方に特に役立つと考えられています。
① 高血圧の方
EPAには血管をしなやかに保つ作用があり、血圧の上昇を抑える効果が期待できます。
② 脂質異常症の方
• 中性脂肪を下げる作用があるため、生活習慣病予防につながります。
• コレステロール値への影響は限定的ですが、中性脂肪対策には有効です。
③ 心筋梗塞・脳梗塞リスクが高い方
• 血栓の形成を抑え、血液をサラサラにするため、動脈硬化や血管の詰まり予防に役立ちます。
• 心疾患の既往がある方は、医師の指導でEPA製剤(処方薬)を使う場合もあります。
④ 炎症性の疾患を持つ方
• 関節リウマチ、アトピー性皮膚炎、喘息などで炎症を抑える効果が研究されています。
• 特にリウマチでは、EPAを含む食事やサプリが関節の腫れ・痛みをやわらげる可能性があります。
⑤ 妊婦さん・授乳中の方
• DHAとともに赤ちゃんの脳や神経の発達に関与します。
• ただし、妊娠中は水銀汚染の心配がある大型魚(マグロなど)よりも、イワシやサンマ、サバなどの小型青魚 がおすすめです。
摂取時の注意点
• 血液をサラサラにする薬(ワルファリン、アスピリンなど)を服用中の方は、出血リスクが高まる可能性があるため医師に相談してください。
• サプリを使う場合は、1日の推奨量(EPA+DHAで約1.5g)を超えないようにしましょう。
EPAは 血液・血管系の不安がある方や炎症性疾患を抱える方 に特に有効です。普段の食生活に青魚を取り入れるのが一番安全で効果的です。
参考
- 「『健康食品』の安全性・有効性情報」 (https://hfnet.nibn.go.jp/column/%E3%80%90%E7%AC%AC19%E5%9B%9E%E3%80%91%E9%AD%9A%E6%B2%B9%E3%80%80/)
- 一般社団法人 オーソモレキュラー栄養医学研究所(https://www.orthomolecular.jp/nutrition/epa-dha/)
この記事は管理栄養士の方に執筆していただきました
井上 希恵